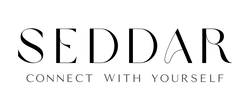茶道や花道のような "道" のひとつに、香道があることをご存知でしょうか。もともとは平安時代の貴族たちの間で嗜まれていたお香文化と、鎌倉時代に入り武家たちの間で広まったお香の楽しみ方が、室町時代以降に融合されたものが香道です。
平安貴族たちは自分を表現する方法としてお香を用いました。オリジナルのお香をつくることは、その人物の感性・知性・財力が表れるものであったため、香りだけで相手に自分のことを間接的に伝えることができたのです。
武家たちははじめこそ香木を聞き比べて(香道では香りを嗅ぐと言わず聞くと言う)産地を当て合うなど、ゲーム性を持ち込んで楽しんでいましたが、やがては香りを聞きながら心を遊ばせ、自分と向き合う時間を深めることで精神を高める、"道" へと昇華させていきました。
飛鳥時代に空間を清める目的で、仏教とともに日本へ伝わった仏用としてのお香は、ここで禅の精神と結び付きます。
それにしても、お香の世界に禅に通ずる香道というものがあると知らなくても、私たちはお香を焚けば自然とリラックスし、自分と向き合う気持ちを呼び起こさせることは、とても興味深いことだと感じます。